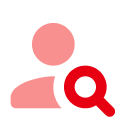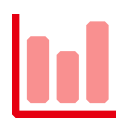エディットスタディとは
2025/09/02
SS(先生)&CEO -Q&A-

目次
- Q. なぜEDIT STUDYでは業務中のノベルティ着用を基本としているのですか?
- Q. 授業や1on1面談でプレップ法1を意識しているのですがうまく使えません。どうしたらいいですか?
- Q. 「信頼関係指数」や「集客状況」などの指数入力は入力後どのように活用しているのですか?
- Q. 「信用と信頼の違い」って何でしょうか?
- Q. PDMCAは理解できるのですが、「M」があるせいで「Be a Pro」として行動基準が低くなる気がします。例えば、「帰宅時の電気消し忘れ」などはMissしてはいけないはずです。
- Q. 小路永SSは昨年も今年も夏からコースを担当していますね。OP外のカリキュラムを運用しているのはなぜですか?
- Q. 小路永SSはどのようなSSに仕事を任せたいですか?
- Q. あまり来塾できない生徒に次の来塾日を決めても来塾してもらえず、裏切られたような気持ちになり自分の気持ちが下がってしまいます。どのように気持ちを整理したらいいですか?
- Q. MGR(マネージャー ※校長を指します)を目指したいのですが、MGRには何が求められてますか?
- Q. オペレーション(OP)の7割は理解できているのですが、残り3割はいまいちイメージがわきません。
- Q. モチベーションを高める上で大切にしてることはありますか?
Q. なぜEDIT STUDYでは業務中のノベルティ着用を基本としているのですか?
A. 理由は大きく分けて2つです。
① 急成長しているベンチャーやスタートアップは例外なく【カルチャー】を明文化し、【タッチポイント】を意図的に増やしているため
② EDIT STUDYブランドを創るため
1つ目は、「急成長しているベンチャーやスタートアップは例外なく【カルチャー】を明文化し、【タッチポイント】を意図的に増やしているため」です。
以下は、メルカリやatama+の創業期にエンジェル投資をしているDCMベンチャーズの日本代表、本多央輔氏がatama+の稲田氏に「最初に伝えたアドバイス」です。
「カルチャーを明文化しなさい。カルチャー作りはもっと後のステージで行うことなんて思うかもしれないが、ユニコーンになったスタートアップたちはみな、最初からカルチャーを強固なものに保ってきた。もっとわかりやすく誰もが覚えられるようなものにして、常に意識できるように!」
投資家から見た時に、「成長可能性が高く投資したくなる法人」もしくは「これから育てていく法人に最初に求めるもの」は「カルチャーを明文化し、常に意識できるようにすること」です。
つまり「同じ【価値観】を共有し、同じ【方向】を向いて走ることができる環境や雰囲気があること」なのです。
「カルチャーを常に意識できるようにすること」、そのタッチポイントがノベルティと考え、基本着用のユニフォームとしています。
2つ目は「EDIT STUDYブランドを創るため」です。
・【明るく】【思いやり】があって何でも相談しやすい
・質問に行けば、あたたかく【笑顔】で答えてくれる
・みんなが同じような空気感、雰囲気で【一体感】を持って【楽しそうに】働いている
生徒からはそんな風に感じてほしいと思っており、それは何より「生徒が勉強しやすい環境づくり」に直結すると判断しています。
(バラバラな雰囲気で、殺伐と働いている雰囲気の校舎で勉強したくないですよね)
上記のような空気感、雰囲気をコスパ良く出せるのがユニフォーム(ノベルティ)着用ですので、多くのサービス業にはユニフォームが存在しています。
分かりやすく言うとディズニーでユニフォームを着用しないで働いている人はいません。
逆に、殆どの塾にユニフォームが存在しないのは個人戦の要素が強いのかもしれませんし、EDIT STUDYは一般的な塾とは全く違う存在であると自負しています。
回答をまとめると、
・成長しているベンチャーやスタートアップを【TTP(徹底的にパクる)】して次なる成長に繋げるため
・生徒にとって勉強しやすい空気感、雰囲気を作り、コスパよく【EDIT STUDYブランド】を創るため
以上の目的から、真剣にノベルティに投資し、基本着用のユニフォームとしています。上記2点の目的を認識した上で着用してもらいたいです!

Q. 授業や1on1面談でプレップ法1を意識しているのですがうまく使えません。どうしたらいいですか?
A. 大切にして欲しいことは2つあります。
①【Point(結論)ファースト】
まずは結論から言い切って話の軸を定めましょう
こちらがスタートです。
テンプレップは造語で、コンサル1年目で習うフレームワークは「プレップの法則」と呼ばれます。
Point(結論)→Reason(理由)→Example(例)→Point(結論)という感じで短く、要点をまとめるイメージです。
②【ナンバリングの徹底(Number)】
何かあれば「2つあって~」「3つあって~」とナンバリングをしましょう
あってもなくても、脳がその数に合わせようと対応するので、自然と話がまとまっていきますし、とりあえず数を言うことで並行してまとめる能力も劇的に上がっていきます。
優れた経営者は、一流のビジネスパーソンや優秀な研究者など、様々な場面で色々な方と交渉やプレゼンをしてきている訳です。あらゆる修羅場を搔い潜って来た人たちが実践してることですので、EDIT STUDYもTTP(徹底的にパクる)していきましょう!
(EDIT STUDYメンバーはSSでもありビジネスパーソンでもありますよね。「分かりやすく伝える技術」というのは、業界問わずビジネスパーソンの必須スキルです)
プレップができると、
・生徒に話が伝わりやすくなる
・個別相談で「出来る雰囲気」を出せる
・社内コミュニケーションが円滑になる
・親御さまへの(メールなど)メッセージが伝わりやすくなる
等々、大きなメリットがあります。
(メッセージやメールなどを添削・閲覧していると普段テンプレップを意識して実践している人とそうでない人がすぐに分かります)
と言うことで、「Be a Pro」として、「Start with CAN」をとにかく実践しながら、「プレップ」を徹底していきましょう!
Q. 「信頼関係指数」や「集客状況」などの指数入力は入力後どのように活用しているのですか?
A. 「仮説思考」を用いて、状況をスピーディーに正確に把握して、「施策作り」や「方向転換」に活用しています。
EDIT STUDYが成長していくために「仮説思考」をとても大切にしています。
▼仮説思考とは
数値に基づき仮説をたてて結果を予測することにより、物事を修正する時間を【短縮】する狙いがあります。
例えば自分が全校舎、全生徒クラスを担当していれば生徒のことをはすべて把握できますが、それは無理です。ですので、皆さんに協力して頂き、現場の【解像度】を高めるために、数値を見て「現場で何が起きているか」「今どんな状況か」仮説を立てています。
▼仮説検証のプロセス
①現在の「数値」を観察・分析する →「KUP95%シート ver5」「集客データ」等ハード面を確認
②仮説を設定し、スタンドアップMTGやMGRにヒアリングする →校舎、クラスの雰囲気や生徒との肌感などソフト面を確認(メールやスタプラも基本的にすべて目を通しています)
③仮説をベースに施策を実行・検証していく →①②を踏まえ、施策作りは主に書籍やケーススタディの論文等を参考にしています
④仮説を修正していく →①(ハード)②(ソフト)から「方向転換」や、次の「施策作り」を実施
このようなプロセスを経ているため、入力に誤りがあると、「そもそも論」で①~④すべてズレてしまいますし、入力に「漏れ」があったりすると仮説検証ができません。
ちなみに指数入力は週末を期限にしており、その理由は日曜早朝から①~④の作業をするために設定しています。
(日曜はEDIT STUDYも休みで社内の相談など発生しづらく、生徒の質問なども少ない、外部企業も休みが多くMTGもなく、仮説検証に集中しやすいからです)
▼Start with CAN
「仮説検証」はビジネスパーソン必須のスキルです。
普段から「数字を見る→仮説を立てる→やってみる」をスピーディーに実行できるように、EDIT STUDYでは「K-upシート」「dropbox」「スタプラ」などの指数データを大切にしています。
こちらを念頭にBe a Proとして「仮説思考」をブラッシュアップしていきましょう!
特にMGRにとって、Valueにあるように仮説思考は必須なのでリマインドしておきます。
Q. 「信用と信頼の違い」って何でしょうか?
A. 信用は「相手に対する理性的な結びつき(客観的)」、信頼は「相手に対する感情的な結びつき(主観的)」 ということになります。
EDIT STUDYのCultureは「助け合える、学び合える、認め合えるCulture」です。
「信頼のCulture」と言い換えることもできます。
組織文化、神経経済学の権威であるポール・ザックは、「成果を上げる国・組織には信頼のCultureがある」と言っています。
ではそもそも「信頼」とは何か?似て非なる言葉「信用」と比較してみましょう。
◆ 信用:相手に対する理性的な結びつき(客観的)
✓ 過去の成果や行動に対する「【一方的な評価】」
✓ 積極的な心の働きかけではなく、成果という【客観的】な材料から導かれるもの
※クレジットカードの審査をイメージすると分かりやすいかもしれません。
◆ 信頼:相手に対する感情的な結びつき(主観的)
✓ 【裏付けのない】ことについて、相手を信じること
✓ 人に期待を寄せる気持ちとその期待に応えようとする気持ち「【双方向のやり取り】」
※「信頼関係」とは言いますが、「信用関係」とは言いませんよね。
つまり「成果を上げられなくても私はあなたを支え続けるよ」というスタンスが信頼ということになります。
生徒対応で考えれば、Rテストで合格しなくても、指示通り勉強してくれなくても、生徒を信じてより良い行動に結びつけられるよう行動を継続した結果、生まれるのが「信頼」です。
そのために面談のアイスブレイクでは「笑顔で雑談」し、「敬意をもって接すること」で、面談が終わった時に「生徒がPositiveな気持ちで未来が見えた状態」で終わることがとても大切です。
EDIT STUDYは生徒への「信頼」を大切に対応していきましょう!
Q. PDMCAは理解できるのですが、「M」があるせいで「Be a Pro」として行動基準が低くなる気がします。例えば、「帰宅時の電気消し忘れ」などはMissしてはいけないはずです。
A. 仰る通りその視点は正しいです。Missには大きく2種類あり、PDMCAの「M」は下記の②に該当します。
①回避できるMiss
(EDIT STUDYで言えば)
・全体メール送信漏れ
・Talknote投稿「いいね!」「Q&A」漏れ
・勤怠漏れ
・経費精算漏れ
・メール返信漏れ
・dropbox入力漏れ
・電気消し忘れ
・コピーミス
・プリント配布漏れ
→全社としては、①のMissが発生しづらいようOP強化、Talknoteでのリマインドにより対応しています。
Wチェックを有効活用し、カルチャーを大切に指摘しあってフォローし合いましょう。
【気づいた人】が対応して、そのことをしっかりFBすることで漏れた人も意識を持って対応してくれるようになります。
習慣化するまで時間がかかることもありますので、【見守り】つつ、FBを継続する必要もあったりします。
②チャレンジによるMiss(学習機会)
(EDIT STUDYでいえば)
・新規事業
・コンテンツ作成
・アジャイル2な生徒、親御さま対応
→新しいチャレンジや答えがない対応はPDMCAをベースにStart with CANでやってみることが大切です。
【リバウンドメンタリティ】を持って、Missからたくさん学び、より良いモノを生んでいきましょう。
①回避できるMissが増えるどうなるか?
→生徒の勉強にロスが出ます。
OPや期限の背景には理由があるので、それを支える人がいる以上各担当者の業務が遅れる、また電気消し忘れなどは法人の経費がかさむため、一人ひとりが相手の立場になって考えたり、一人ひとりのコスト意識が大切だったりします。
まとめると、「どこまで一人ひとりが【当事者意識】を持って対応できるかがEDIT STUDY成長のカギ」となります。
Q. 小路永SSは昨年も今年も夏からコースを担当していますね。OP外のカリキュラムを運用しているのはなぜですか?
A. 「【たくみ】」から「【しくみ】」に移行するクリエイディブ・ルーチンのためOP外の対応をしています。
クラス替えにより講師が変わらない夏からコースで(SAを大前提に)来年度に向けて【実験主義】でクラス運営をしています。
今年度は既に必修編の全範囲が終わったので、週に1度の授業を「過去問対策1on1 Day」の自学自習スタイルにチャレンジします!
▼「たくみ」から「しくみ」とは
『「たくみ」から「しくみ」のイノベーションモデル』はEDIT STUDYのOP進化を支えているモデルです。
【守】しくみ:教えを忠実に守り基本の型を習得する(OP≒ルーチン)
【破】過程:他の型などを取り入れ新しい型を模索する(OP外≒クリエイティビティ)
【離】たくみ:型から離れて独自の自由な境地を切り拓く(新たにOP化する対象)
そもそも創業時からEDIT STUDYは 村山 雅俊SS、個人事業主dietstudy時代の指導スタイル(たくみ)を「Vision実現に向けて、より多くの生徒に、より多くのSSが、同クオリティで届けることができる」ことを大切にOP(しくみ)を進化させています。
そのために電子ボード・PPT・選択科目動画等に投資しながら、並行して合格マインド・PPC・1on1面談導入と、新たなチャレンジを繰り返して、生徒により良いサービスを提供しています。
守破離の「破」のフェーズに入ることで【新たなチャレンジ】が生まれますし、そのような発想は心理的安全性が確保されていて創造性が発揮できる環境でないと難しいので、EDIT STUDYはカルチャーを大切に、誰もがStart with CANでチャレンジできる土壌を作っている訳です。
より良いものを生み出すという目的を最優先に、リスペクトを持ちながら率直にFBできる関係性も大切にしている訳です。
そして「たくみ(破)」フェーズに入って新しいモノが生み出せたら、Be a Proとして誰もができる「しくみ(守)」に還し、『「たくみ」から「しくみ」のイノベーションモデル(守破離の循環)』をONE TEAMで高速回転させて、より良いサービスを【雪だるま式】で大きくして進んでいく、これがEDIT STUDYのOP進化の最大のポイントです。
OPを運用する業務は一般的にルーチン化しやすく「つまらない」と言われがちですが(採用活動でも質問されます)、生徒という対人の仕事で【感情】を扱うため変化が多いですし、さらにEDIT STUDYのOPは『「たくみ」から「しくみ」のイノベーションモデル』を前提にしているので、カルチャーを大切に、【みんなの声】を反映して進化していくので、変化を楽しみながら働くことができるのです!
Q. 小路永SSはどのようなSSに仕事を任せたいですか?
A. 意思決定の基準としては以下になります。
▼意思決定の基準(任せたいか、どうか)
・進言する人が法人の当事者か【Be a Pro】
→自身のエゴではなく、【顧客のため】、【法人】の可能性や成長を考えて進言しているか。
【評論家】ではなく、【実行者】か。カルチャーやValueを体現してくれている人か。ココは大前提の部分です。
・「【成功】」ではなく、「【成長】」に繋がるか【Start with CAN】
→このOP運用を現場に出て小路永が担当したら成功可能性は高いけど、自分が成長することはあまりない。
SSに任せた方がSSも、みんなも成長するし、そっちの方が嬉しいし、楽しいです。
・「クリエイティブ・ルーチン」に繋がるか【ONE TEAM】
→任せることでシステム化に繋がり、誰でも出来るようになり、【より多くの人】にサービスが届くようになる。役割も継承されていき、みんなの成長に繋がりますよね。
▼任せた後に注意してること【助け合える、学び合える、認め合えるカルチャー】
・必要な道具や経費は出すが、【口】を挟まない
→任せるということは信じて見守ることなので、基本的に自分からは口を挟まない。
ただし、相談事があった場合は、全力で対応するし、苦しそうなフラグが立っていたら手を差し伸べる。
これがカルチャーです。
・「【期待値】を下げるスキル」を使って許容度を上げ、見守る
→これは期待していない訳ではなく、スキルとして期待値を下げることを指す。
自分がやってきたことを任せるとなると「なんでこんなこと出来ないんだ」とか人間なので思うこともあるけど、その感情を持つことによって良いことは誰にもありませんよね。
(この感情で行われるアドバイスほど伝わらないモノはないですよね)
※ちなみにこのスキルは「生徒対応(生徒のモノサシ)」で多用し、PFに繋げつつ、必要な指摘もしているので育成スキルとして使ってみて下さい。
そもそも事実として、自分が出来ることを他の人がすぐに出来るわけではないし、自分だって、みんなの【サポート】があったから出来るようになった訳だし、自分にできなくて、他の人にできることもたくさんあるし、だからこそ【法人】をやっているし、ONE TEAM(性善説&リスペクト・ベース)で運営している訳です。
▼法人の【器】は、代表の【器】以上になり得ない
スキルとして期待値を下げ(許容度を上げ)、信じても見守り、成長に必要なサポートを正しくすることで、ゴールに伴走する。それが自身の器を大きくすること=【法人の成長】に繋がると判断して、上記の意思決定プロセスとなっています。
こちらは校舎やクラス、生徒の成長でも同じことが当てはまりますので、ONE TEAMで器を大きくして、成長していきましょう!
Q. あまり来塾できない生徒に次の来塾日を決めても来塾してもらえず、裏切られたような気持ちになり自分の気持ちが下がってしまいます。どのように気持ちを整理したらいいですか?
A. 来塾できないことまでをシミュレーションして、お互いに共有しておきましょう。
<トーク例>
・あまり想像したくないけど、約束した日に来塾できない可能性も当然あるよね
<フィードフォワード>
・そんな時は自己嫌悪などせずに、「行けませんでした」など、簡単にメッセージをくれればOK
・また次に来れた時でもいいし、電話でもいいので、次にどのように進めていくか1on1で話していきましょう
<効果>
生徒:【自己嫌悪】に陥りづらく、連絡もしやすくなるため、また来るきっかけを持てる
講師:【一憂】せずに、連絡をもらえる可能性を高め、次の作戦を立てやすくなる
Q. MGR(マネージャー ※校長を指します)を目指したいのですが、MGRには何が求められてますか?
A. 組織のベクトルと同じ方向を向き、【ファクト】に基づき【マクロ視点】で意思決定すること(シンプルに言えば仮説思考です)
MGR Valueを常に体現することが求められますので、まずはカルチャーガイドを見て欲しいのですが、ここでは視点を変えて(EDIT STUDY含めて)一般的にマネージャーと言われる人に求められることを1つだけざっくりとシェアしておきます。
(主にマネージャーとメンバーの違いです)
まず前提として、組織のベクトルと同じ方向を向き、メンバーと共に【チームの成果】を最大化することがマネージャーの役割となります。
(組織のベクトルと異なる方向を向いてる人はそもそもマネージャーにはなることができません)
メンバーは自身の担当エリアで成果を上げることが仕事なので、必然的に【ミクロ視点】で判断していくことになります。(メンバーはその役割りが正しいのです)
マネージャーは各メンバーの担当エリア全体の(数値や本部からシェアされた過去データなど)ファクトと、メンバーとの対話に基づき、「マクロ視点」で適材適所等を考え抜き、チームの成果を最大化することが役割となります。
逆にメンバーと同じように「ミクロ視点のみ」や、「ファクト」ではなく「その場の感情やイメージ」に流されて判断していると、チームの成果は最大化されず、マネージャーとメンバーと役割分担をしている意味はなくなります。(そもそもマネージャーは不要ですよね)
上記のように一般化されたマネージャーの役割から、EDIT STUDYでのMGRの役割をイメージすると、これからMGRを目指すMEMとして、できることが見えてくれると思いますので、参考にして下さい!
Q. オペレーション(OP)の7割は理解できているのですが、残り3割はいまいちイメージがわきません。
A. EDIT STUDYが大切にするOPの7割は【システム面】(集客フロー・授業・1on1運営面)、3割は【ソフト面】(質問やメールなど生徒対応)です。
EDIT STUDYの仕事はセントラルキッチン方式の飲食店をイメージしてもらうと分かりやすいです。
セントラルキッチン方式とは、先に調理を完了して冷凍した状態で各店舗に送り、店舗では解凍したり、温めたりして、スタッフの方がお客様に「【気持ちを込めて】」声をかけたり、配膳したりしながら、料理の【クオリティコントロール】をする方式です。そしてスタッフがお客さまから頂いた意見は様々な形でセントラルキッチンに【フィードバック】され、調理がブラッシュアップされていきます。
EDIT STUDYで言うセントラルキッチンは集客OPだったり、授業ではカリキュラムを全員が同じように授業できるようPPT・動画・Rテストやプリントを作り込み、同じクオリティとベクトルで生徒の気持ちに寄り添い、生徒の気持ちを前に進める1on1を実施できるようにPPCを開発&トレーニングを重ねており、こちらがOP7割(セントラルキッチン)に該当します。
残りの3割は普段から対話式授業や1on1を通してコミュニケーションをとって【信頼関係】を築いている担当SS(先生)しかできないソフト面の対応です。生徒個別の性格や学力を考慮しながら質問対応したり、メールを返信したりと、担当ではないとできないソフト面の対応が3割程度あります。(PPCはあくまでも軸ですので、1on1の中で多くのソフト対応がありますよね)
大きく言うとOPにはないような緊急度が高く、その場で意思決定してスピーディー対応することが3割に該当するイメージです。人対人の仕事のため、イレギュラーが数多く発生するので、【柔軟性】や【曖昧耐性】を採用基準に入れています。
EDIT STUDYの方針としては、みんなの困りごと等をフィードバックしてもらい、スピーディーにOPに落とし込むことでより良い生徒対応を実現していきます。フィードバックをしやすい環境を整えるためにカルチャーにも投資しているので講師や生徒の困りごとは「大大大歓迎」です!
Q. モチベーションを高める上で大切にしてることはありますか?
A. モチベーションを高めようと意識しているわけではありませんが、毎朝「レッドクイーン理論3」をリマインドしています。
一言でいうと、レッドクイーン理論とは「同じ場所に留まるために、進化し続けなければならない」進化競争の法則です。
これは経営学やビジネスでも使われる考え方で、企業が市場で生き残るためには、新しい技術や戦略を取り入れ続けなければならない、という意味で比喩的に使われます。
EDIT STUDYはベンチャーですので、一人ひとりが圧倒的当事者意識を持って進化し続けることがサバイブする大前提になります。
- プレップ法
プレップ法(PREP法)とは、意見や考えをわかりやすく伝えるための文章・スピーチ構成法の一つです。
Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論) の流れで話すのが基本です。
PREP法の構成
Point(結論)
最初に自分の主張や結論をシンプルに述べます。
例:「私は英語の学習には音読が効果的だと思います。」
Reason(理由)
なぜその結論に至ったのか、根拠を述べます。
例:「なぜなら、音読は発音やリズムの練習になるからです。」
Example(具体例)
実際の事例や経験を挙げて、説得力を高めます。
例:「例えば、毎日10分音読を続けた生徒は、スピーキングのテストで高得点を取れるようになりました。」
Point(結論の再提示)
最後に再度結論を示し、印象を強めます。
例:「したがって、英語学習には音読を取り入れるべきです。」
特徴
話の順序が明確で聞き手に理解されやすい
結論を最初と最後に示すことで説得力が高まる
プレゼン・面接・英作文など幅広く活用できる
↩︎ - アジャイルとは、ソフトウェア開発やプロジェクト管理における 考え方・手法 の一つで、「変化に対応しながら、段階的に価値を届けていく働き方」を意味します。
顧客対応に当てはめると、アジャイルな顧客対応とは「速さ・柔軟さ・協働性を重視した、変化に強い対応スタイル」と言えます。
↩︎ - 「レッドクイーン理論(Red Queen Hypothesis)」
レッドクイーン理論とは生物進化に関する考え方の一つです。
基本の考え方
由来
ルイス・キャロルの小説『鏡の国のアリス』に登場する「赤の女王(Red Queen)」が由来です。
その女王はアリスに「同じ場所に留まるためには、全力で走り続けなければならない」と言います。
進化論的意味
生物は生き残るために常に進化し続ける必要がある、という比喩です。
周囲の環境や他の生物(天敵、寄生者、競争相手)も進化し続けているため、ただ現状維持では取り残されてしまいます。
生物学での具体例
寄生者と宿主
ウイルスや細菌が進化して感染力を高めれば、宿主(人間や動物)は免疫系を進化させなければ生き残れません。
捕食者と被食者
肉食動物が速くなれば、草食動物も逃げるために速くならざるを得ない。
ポイント
「競争相手も進化するので、自分も進化し続けなければ生き残れない」
つまり、進化は**相対的な競争の中での“生存戦略”**という考え方です。
↩︎
「エディットスタディで働く」を
もっと知る
“科目の講師”ではなく、
“成長の伴走者”に興味があるなら。