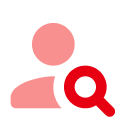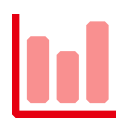エディットスタディとは
2025/09/02
EDIT STUDYのイベント&社内用語

共通テスト・得点報告オンラインイベント(任意参加)
ほぼすべての生徒さまが受験する共通テスト。
毎年、本当に多くのSSがオンラインで集まってくれて、生徒さまからの得点報告メッセージに「労いの言葉」をかけたり、「叱咤激励」を行うことで次の入試に向けて伴走します。生徒さまからは「共テは失敗したけど、あの時のメッセージがあったから切り替えて志望校に合格できた!」とEDIT STUDYでの思い出になっていることが数多くあります。
(オンラインイベントの様子)

EDIT STUDY内で使用される社内用語(大切にしている用語)
【名は体を表す】
そもそも人は、名前のないものについて、深く考えることはできないし、逆に名前を生み出すことで、新しい概念についてもイメージできるようになります。ですので、まずは対象の「定義」を考え、みんながイメージしやすいカタチにして、生徒が聞いても分からないように名前をつけています。
みんなが同じイメージを持ち【同じ絵を描く出発点】が名前なので、こだわって、大切にしています。
【ポジティブサイコロジー】
弊社の顧問である松隈氏の研究分野。医学博士、公認心理師。慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程修了。ポジティブサイコロジーの科学的知見に基づき、組織作り・PPC・合格マインドが行われており、EDIT STUDYのコアと言えます。
【コーチャブル】
スティーブ・ジョブスのコーチの言葉。何かを良くするためのアドバイスを容易に受け入れ、改善することができる。うまくいかなければ相談などしながら粘り強く上手くできるよう対応していくことができる。SSにも生徒にも求められる資質。
【PF】(ポジティブ・フォーカス)
褒めて、認めること。EDIT STUDYの生徒対応の基本スタンス。
【SA】(成績上げる)
合格保証対象になってもらい、成績を上げること。
【信頼関係指数】(前期)
「KUP95%シート」に毎週末数値を入力し、「信頼関係指数1~5」を継続率のKPIとしています。
<信頼関係指数>
5→(3⇒4のプロセスを経て)生徒から雑談 or 息抜きの方法を相談
4→生徒から積極的にSAに向けた相談をしてくれる
3→SSと決めたアクションプランに対して積極的に行動
2→SSと決めたアクションプランに対して消極的に行動 or 信頼関係性を築くために雑談がメイン
1→SSからのコミュニケーションをストレスに感じている or 出席できない
※アクションプラン
→SAを主な目的とした①学習習慣②メンタル③生活習慣の3つを含む
→SAの中には「Rテスト合格」や「保証対象になる」こと以外の「各生徒のSMAゴール」含む
→SMAゴール(明確で、測定可能で、達成可能性がある)とは「Rテスト目標点個別設定」「出席率」「自習室利用」など
※KPI:重要業績評価指標、ココでは継続率を決める前プロセスの効果指数
【SA到達率】(後期)
Vision実現に向けて、生徒の第1志望群合格を実現するために、毎週末1on1終了時に「SA到達率」(内訳「①(M)マインド」「②(IN)インプット」「③(OUT)アウトプット」)を入力していきます。
各生徒の第1志望群の合格(1 早慶上智/2 GMARCH・関関同立/3 成成明学獨國武西南/4 日東駒専/5 その他)から(「時期」や「伸びしろ」を含めて)逆算した上で「SA到達率シート」を入力し、志望校合格のKPIとしています。
【MIX MTG(ごちゃまぜミーティング)】
月水金TEAMと火木土TEAM、校舎をまたいでSS同士コミュニケーションをとり、生徒のためにBe a Proとして成長していきたいという想いからはじまった月1回(月末)のMTG。生徒対応への悩み等をテーマにSSがONE TEAMで集い解決策を探っていきます。
普段あまりコミュニケーションとっていないSS同士のMTGですが、時間が30分と限られていること、かつオンラインということで、事前準備を含めたファシリテーション能力を向上させる機会にもなっています。
【PD】(ポテンシャル・ドロップアウト)
信頼関係指数が1~2のESを継続する可能性が低い生徒のこと。もしくは来塾が難しい生徒。
【CX】(カスタマーエクスペリエンス)
顧客が心理的かつ感覚的な価値を感じ、顧客エンゲージメント(企業やブランドに対する信頼や絆)を高める体験のこと。CSは顧客満足度を高めるというニュアンスになり、満足度を高めるというより、より良い体験をしてもらうという、よりポジティブなメンタリティを持つためCXを使用する。
【KPT】-1on1-
生徒との週に1度の1on1面談のフレームワークになります。
「Keep(継続すること)」「Problem(改善が必要なこと)」「Try(取り組むべきこと)」の順に検討し、今後のアクションを決めるというやり方です。
【PDMCA】
Plan(計画)→ Do(実行)→ Miss(失敗)→ Check(評価)→ Act(改善)のこと。
PDCAの真ん中に「M(失敗)」を置くことでチャレンジしやすく、失敗した後にすぐに起き上がるリバウンドメンタリティをもって仕事に取り組むことができます。
【CT】(チェックテスト)
体験授業や無料個別相談を実施するためのテスト。評価項目に基づき、高いハードルが設定される。
【CTO】(チーフ・テレアポ・オフィサー)
集客期に彗星の如く突如として出現する。資料請求先に無料個別相談のテレアポをし、予約を大量に獲得する。
【勝負の神様は細部に宿る】
勝ち負けを分けるのは『これでいっか』『後でいっか』という小さなゆるみであることがほとんど。
OPの徹底度を大切に、集客期にはメールのW体制を徹底するなど、細部にこだわった対応をする。
【コネクティング・ザ・ドッツ】
『将来どんなことに役立つかはわからなくても、おもしろいと思える「点」を増やしておくために、新たなチャレンジを繰り返しておくこと。
その「点」と「点」が後からどうつながるのか分からないけど、意識的に、意図的につなげていくこと。過去の一見すると無関係な「点(経験)」が今になってつながり、新たな大きな可能性につながるということ』です。EDIT STUDYはチャレンジすることで点を意識的に増やしています。
【グッドサイクル】
成功の循環モデル、4つの質がクラスや校舎の雰囲気を決める、関係の質を高めることがすべて。
【セルフ・エフィカシー(根拠なき自信)を持つこと】
ゴールに向けて一人ひとりがセルフ・エフィカシーを持つことで「自分たちはこのゴールを達成したい。そして実際に達成できる気がする」という認知をチームにデザインすることでより強固なONE TEAMとなる。
スキーを例に挙げると、ゴールに向けて滑り切る必要があるのに不安で体重をうしろにかけると転んでしまいますが、セルフ・エフィカシーを持って、前傾姿勢を取り、前に体重をかけると進みます、進みながらターンしたりブレーキをかけたりすることでゴールまで滑り切ることができる。ここで言うターンやブレーキは前に進み、ゴールに向けて滑り切る手段になります。
集客で言えば、セルフ・エフィカシーを持ち、前に進むことがOPのカイゼンや応酬トークのブラッシュアップに繋がる。一人ひとりが「Be a Pro」として、ゴールに対してセルフ・エフィカシー(「できる気しかしない」という根拠のない自信)を持つことで、集団的エフィカシー(「自分たちはやれる、やれる気しかしない」)溢れる熱量の高いONE TEAMを創ることが大切。
【常に「自然性」でいること】
「自然性」とは京セラ創業者稲盛和夫氏の書籍や講演の中で頻繁に出てくるキーワード。以下原文ままシェアしますが、簡単に言えば「自ら燃えろ、せめて可燃でいてくれ、不燃はいらない」ということなので、Be a Proとして「自然性」を意識することが大切。
原文まま——–
<「自然性の人」となる>
物質には、「可燃性」「不燃性」「自然性(じねんせい)」のものがあります。
同様に、人間のタイプにも火を近づけると燃え上がる「可燃性」の人、火を近づけても燃えない「不燃性」の人、自分からカッカと燃え上がる「自然性」の人がいます。何かを成し遂げようとするには、「自ら燃える人」でなければなりません。
自ら燃えるためには、自分のしていることを好きになると同時に、明確な目標を持つことが必要です。
私のような経営者であれば、自分の会社をこうしよう、ああしようとつねに考えています。仕事に就いたばかりの若い人も、自分の将来に夢を描き、こうなりたい、ああなりたいと考えていることでしょう。
しかし中には、ニヒルというか、冷めきった顔をして、まったく燃え上がってくれない若者がいます。周囲がいくらカッカと熱くなっていても燃え上がらないどころか、相手の熱まで奪ってしまいそうな、「氷のような人間」がときたまいるものです。
こういう人間は困りものです。
企業の場合でも、スポーツチームの場合でも、そのように燃えてくれない人が一人でもいると、全体が沈滞した雰囲気になってしまいます。
だから、私はよくこんなことを思ったものです。 『「不燃性の人」は会社にいてもらわなくても結構だ。私が近づかなくても勝手に燃えてくれる「自然性の人」であってほしい。少なくとも燃えている私が近づけば一緒になって燃える「可燃性の人」でなくてはならない』
【凡事徹底】
「普通のことをちゃんとやる」「徹底してやり続ける」ことが最終的には、非凡な成果をもたらすという意味で、パナソニック創業者の松下幸之助さんの座右の銘として有名な言葉。(イチローさんも「小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行くただ一つの道」など言ってることは有名)
【「期待値を下げるスキル」を使って許容度を上げ、見守る】
これは期待していない訳ではなく、スキルとして期待値を下げることを指す。
生徒の行動が変わらないと「なんでやらないんだ?」とか人間なので思いますが、その感情を持つことによって良いことは誰にもありません。伴走しつつ、見守るスキルになります。
【感情労働】
生徒や親御様の気持ちに寄り添い、安心感を与え、一緒に伴走してゴールを目指すEDIT STUDYの労働スタイル。ちなみに頭脳労働の知識やスキルはAIへ、肉体労働はロボットへと移転される中で、労働の価値は感情労働移転すると言われている。IQ(Intelligence Quotient)よりも
EQ(Emotional intelligence Quotient)とも言われたりする。
【エモロジ】
エモーショナルとロジカルを合わせた言葉。人はエモだけでも、ロジだけでも動かない。状況に合わせてエモとロジのグラデーションを最適化する必要がある。
【テンプレップの法則】
人に分かりやすく物事を伝えるフレームワーク。ナンバーをドヤることで信頼感を増すことが出来たりする。Tはテーマ→Nはナンバー(数)→Pはポイント、要点(結論)→Rは理由(Reason)→Eは具体例(Example)→Pはポイント、要点(結論)。
【100-1=0】
ブランドを築くのは大変なプロセスだが、1度の過失によりそのブランド価値は0になります。
まだまだ成長過程の未熟なベンチャーなので、その過失によりサバイブできなくなる可能性あり。
【5S】
生徒が勉強しやすく、みんなが働きやすい環境つくりのマネジメント手法。
整理:必要なものと不要なものを分け、不要なものを捨てること。
整頓:必要なものがすぐに取り出せるように、置き場所、置き方を決め、表示を確実に行うこと。
清掃:掃除をして、ゴミ、汚れのないきれいな状態にすると同時に、細部まで点検すること。
清潔:整理・整頓・清掃を徹底して実行し、汚れのないきれいな状態を維持すること。
躾 :決められたことを決められたとおりに実行できるよう、習慣づけること
【ONE TEAM採用】
採用検討者を校舎に招き、ランチをしつつカルチャーを伝えることで、入社確度を高める
【リファラル採用】
SS紹介→知人が入社してくれた場合、紹介してくれたSSに謝礼金5万→1年働いてくれた場合、更に5万円が支給される制度。
【ONE TEAM弁当手当】
集客期の土曜日(不定期)にみんなでランチお弁当を食べ、ONE TEAMのきっかけとする
【オフサイトコミュニケーション手当】
「カルチャー」を浸透させる全社イベントやカルチャー浸透の企画など、コロナで一時休止も2022年カタールW杯で再開。
【SS-1グランプリ】
PPC認定&更新テストの結果を踏まえ、年末の全社総会にて1on1を最も有効に活用できるNo1のSSを決めるグランプリ。2022年~スタートし、賞金&トロフィーが授与される。
「エディットスタディで働く」を
もっと知る
“科目の講師”ではなく、
“成長の伴走者”に興味があるなら。